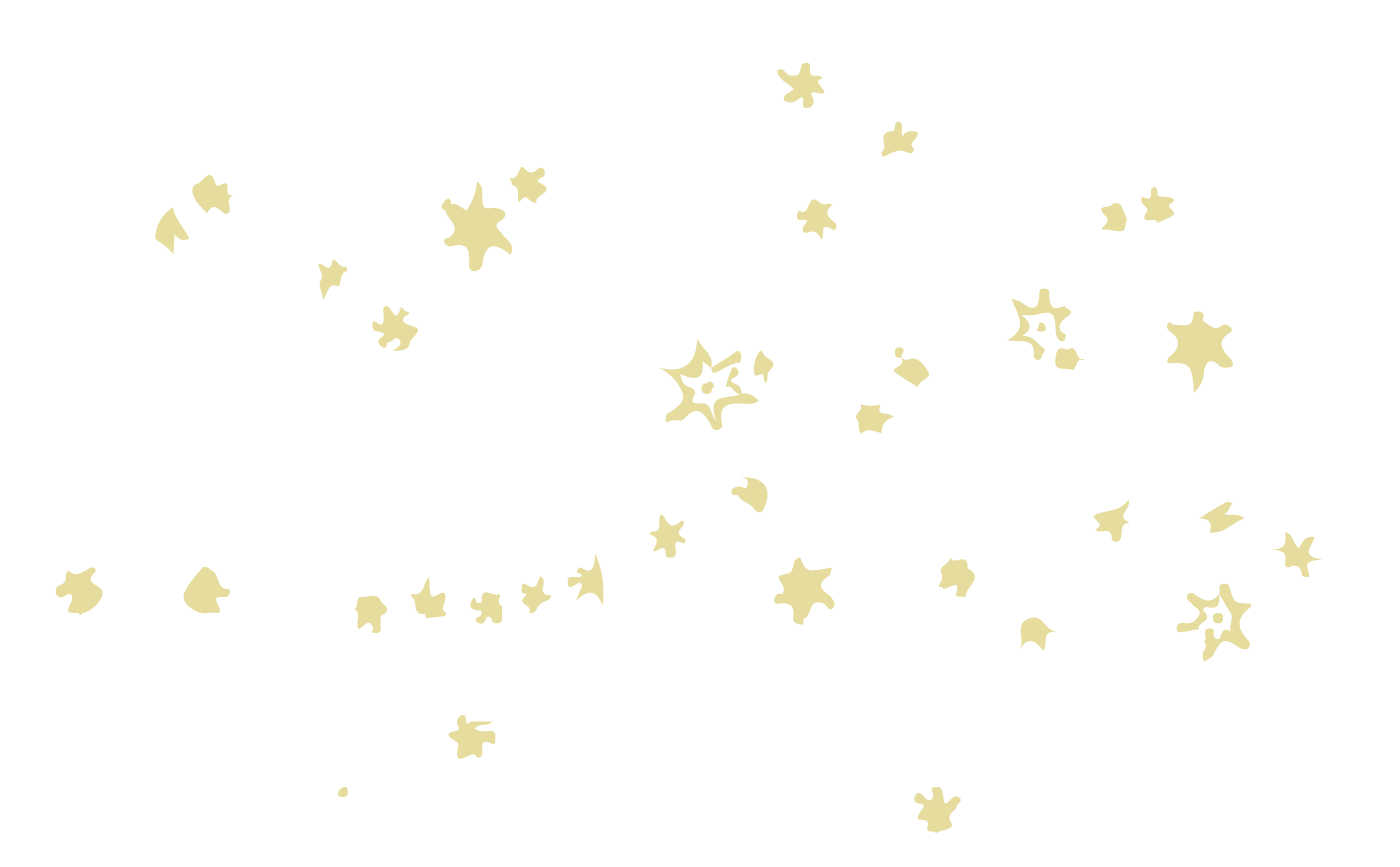マネジャーには、部下が仕事で困っている時に手助けする役割があります。目的の達成を保証することが暗黙の期待だからです。
見通しの悪い状況でリスクを取ってアクションを選択することは、マネジメントの基本のひとつです。
しかしマネジャーの一部には、ノルマを課すことに徹して、まったく部下と共同でワークすることがない人もいます。
仕事の丸投げは、よくある機能不全です。
組織の視点からは対処が不可欠であるものの、部下の立場からは状況を変えづらい問題でもあります。
忙しいのではなくリスクを嫌う
丸投げの隠れた意図は責任回避です。
マネジャーが「失敗したのは部下である」「部下の仕事に関与していないとは言えない」と主張するケースが典型例です。
そのマネージャーは仕事内容にリスクを感じ、自分が関わる範囲をできるだけ狭めるように立ち回っています。
タスクの進め方を選択するような判断を求められれば避けようとしますし、選択の根拠となるような状況分析に見解を述べたくもありません。
このような挙動は、ストレス耐性が低いことが原因で、マネージャーが仕事から逃げている状況を示しています。
性格のバラつきと責任の重さによって反応にもバリエーションがあります。
極端な場合、部下が話を始めようと声をかけただけでその場を去ります。これは絶対に関わらないという強い拒絶反応によるもので、進め方の工夫によって改善を見込めない最悪の状況です。
同時に、責任のない雑務を積極的に引き受ける挙動も観察できます。時間がない状況を作れれば、責任のある仕事に手が回らなくても説明がつくからです。
説明責任を求めることで機能不全をチェックできる
多くの場合、管理職には説明責任があります。上級マネジャーの立場であれば、日常的に状況報告を求めることにより、機能不全は早期発見できます。
ポイントは、業務で起きているできごとを3分ほどかけて説明できるか?という課題です。
メンタルの弱い人は、構造的なストーリーで事実認識することが特に苦手で、時間をかけて練習しても上達しません。
極端に短いワンフレーズ説明しかできず、追加の説明を求めると今度はとりとめなく話し出します。
本人は、思い出せるのだから理解しているのだと錯覚していますが、仕事にどのような影響があるのかを評価できていなければ状況描写には失敗しています。
当然のこととして、現実認識に混乱がある人は行動判断を的確に下すことにも難があります。
現に丸投げが起きているときには、マネジャーは仕事のできごとを描写することもできませんし、その説明を求められてもいない環境と言えます。
ストレスに弱い人はマネジャーに適していない
そもそも管理職は方針と現実の矛盾や関係者の軋轢を調整することが中心的な役割です。対人ストレスも当然強くなります。
同情的に状況を見れば、マネジャー自身が強い苦痛に耐えているケースが大半を占めるでしょう。
ストレスを感じやすい人物はマネジメントを手がけるべきではありませんし、不適応が表面化した場合にはマネジャーを降りた方が健全です。
仕事の丸投げが起きているケースでは、業務運用のハンドルを手離してしまっているため、いずれは失敗します。
残念ながら失敗をかんたんに許容してはもらえないのがマネジャーの役割です。
時間をかけて立場が悪くなる展開は、不安を感じやすい人にとってはメンタル疾患への一本道です。
精神疾患にかかった場合、結局は環境を変えてストレスを減らさなければなりません。対策が遅れると症状も重くなり、治る見込みもなくなっていきます。
異動による解決
マネジャーが仕事の丸投げをしている場合、根本的な問題はそのマネージャー自身ではなく人選ミスが原因です。
本人に改善を直接要望しても事態は改善しないでしょう。
キーパーソンはマネジャーの上司です。健全な組織であれば、上級マネジャーはマネジメント不良にも責任を負っています。 上級マネジャーにコンタクトする手段がない場合には、レポートラインに近い別のマネジャーに相談することが次善策です。
採用ミスはマネジメント不良に直結
マネジメント不良の対症療法はマネジャーの交代です。
候補がいるなら解決に期待を持てますが、適任の代役がいない可能性もあります。
企業の昇進・選抜は、一定の実績がある従業員から選ぶ方式が大半です。 そのため、そもそも選抜の際に適任の候補が手薄だったことがマネジメント不良の遠因になることが多くあります。
人材プールの希薄化はいずれ組織行動のトラブルとして表面化してきます。 結論として、丸投げ問題の直接の原因は採用の失敗です。マネジャーの業績は個々人の性格の影響が大きいため、採用の際の人材鑑定に失敗すると人材プールが希薄化し、マネジャーも消極的な人選にならざるを得ないのです。
よってマネジャー不適格と判断しても代役がいない場合、採用からやり直しになります。
中小企業など人員増の余裕がないケースでは、人員削減もセットで必要になります。
楽観性に着目したチーム作り
仕事の丸投げを解決するには、不安を感じやすく神経質な人をマネジャーにアサインしないことです。同時にこれは、楽観的な人物を採用時に一定の割合で含んでいなくてはならない、という制約でもあります。
もちろん、会社の文化やプラクティスにより、神経質な人でもマネジメントできる方法論がある、という立場は可能です。有意義なチャレンジです。その場合、クリアなロジックを持つようにしてください。
これまでのところ、そのような方法に科学的なコンセンサスはありません。また、丸投げが起きているという事実とは矛盾しています。
科学的な性格分析がチームと従業員を守る
マネジャー適格の基準が適切でなければ、人を入れかえても同じトラブルを延々と繰り返します。
個々人の人格特性と仕事の役割のミスマッチは、メンタル疾患の直接の原因でもあります。適切なアサインは、チームのパフォーマンスと同時にマネジャーの精神衛生面のセーフティネットでもあるのです。
100年にわたる科学研究の末にビッグファイブの5要素が特定されたことで、いまでは性格を的確に評価する方法が明らかになりました。 仕事の丸投げは、神経症傾向というパラメータと関連しています。他の4つのパラメータと関連が深いビジネス現象もあります。
性格理解の進歩については、 ていねいにわかるビッグファイブ で解説しています。
信頼性・神経症傾向・開放性・外向性・協調性の5要素に着目することで、人は自他ともに性格を評価する力を最大限発揮できます。
正しい尺度で評価するには、日常用語による素朴な人物描写を一度アンラーンする必要があります。そのためにはツール整備が有効です。
ディサイダー®
は、人格に着目する優れたチーム作りを実現するフレームワークです。
手軽に採用活動に使える性格適性検査はもちろん、世界初、緻密な分析のための相互評価機能の商用搭載も実現。目的に応じて柔軟に導入できます。